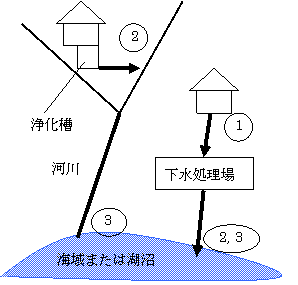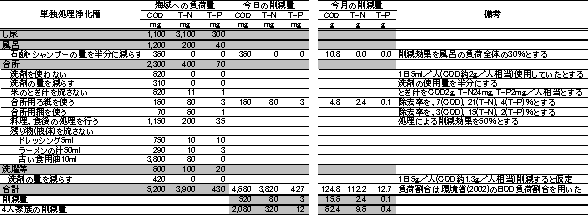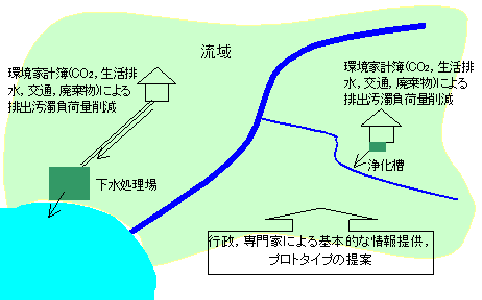(公共用)水域に流入する1人あたり汚濁負荷量および生活排水の環境家計簿に関する研究 (in Japanese)
Domestic wastewater pollutant loads and water quality in the river, lake
and sea
(This page is only in Japanese. Please refer to my publication list or contact me if you want to find information in English.)
by Yoshiaki Tsuzuki, ReCCLE, Shimane University
(1) (公共用)水域に流入する1人あたり汚濁負荷量の考え方
(公共用)水域に流入する1人あたり汚濁負荷量は、様々な生活排水処理の種類があり、例えば、ある河川の流域で生活排水による汚濁負荷量を考えた場合に、河口から海域に流入する地点での公共用水域の汚濁負荷量への寄与割合は上流と下流では異なるであろう、ということから考えた指標です。
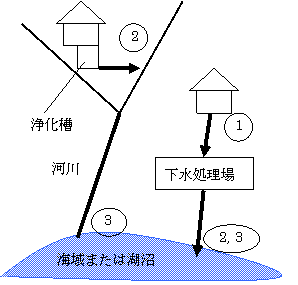 |
生活排水の汚濁負荷量に関する指標として、従来から、発生原単位、排出原単位が用いられてきている。発生原単位は、家庭で発生する汚濁負荷量で、通常は1人あたりの値が用いられる。これに対して、排出原単位は、オンサイト処理(汚濁が発生する地点での処理の方法)が行われている場合には、処理後に排出される汚濁負荷量の1人あたりの値である。下水処理場、農村集落排水処理施設などの集合処理の場合には、処理施設での処理後の1人あたりの汚濁負荷量の値となる。
一方、公共用水域に流入する1人あたり汚濁負荷量は、対象水域を想定し、その水域に流入する汚濁負荷量に、生活排水がどの程度寄与するかを表す数字である。図1では、公共用水域を海域または湖沼への流入部分をイメージしている。大きな河川などでは、河川内のある地点を想定することも可能である。
当初は、公共用水域に流入する1人あたり汚濁負荷量という言葉を用いていた。しかしながら、水域が必ずしも公共用水域ばかりではないことを考えて、現在は、(公共用)水域に流入する1人あたり汚濁負荷量と、(公共用)にカッコをつけるなどしている。
現在まで、海老川(千葉県船橋市)、都川などの千葉市(千葉県)の都市内河川、朝酌川などの松江市(島根県)の都市内河川などについての解析を行ってきた。
|
| 図1 従来の発生源単位(①)、排出原単位(②)と公共用水域に流入する1人あたり汚濁負荷量(③)(出典:都筑 (2005a)を一部修正) |
(2) (公共用)水域に流入する1人あたり汚濁負荷量
| 表1 公共用水域に流入する1人あたり汚濁負荷量(出典:都筑 (2005a)) |
 |
表1は海老川流域と千葉市について、公共用水域に流入する1人あたり汚濁負荷量を算定した結果である。海老川の場合には、流域全体をまとめて計算したので、COD,
TN, TPの数字が各排水処理種類について1つのみ示されている。千葉市については、流域を15の小流域に分割して計算した。排水処理の種類が同じでも、BOD,
CODの公共用水域に流入する1人あたり汚濁負荷量の数字は、小流域によって「範囲」の欄に示すように、おおよそ2~3倍の幅があることが分かった。
(3) 生活排水の環境家計簿
生活排水の環境家計簿は、各小流域における生活排水処理種類別の「公共用水域に流入する1人あたり汚濁負荷量」を元にして、家庭での汚濁負荷削減対策の効果を一覧表で示し、さらに、削減対策を行うことによる効果を算定することができるようにした表である。地球温暖化防止を目的とする二酸化炭素(CO2)削減をテーマにするいわゆる環境家計簿の発想を、水質汚濁の軽減を目的として用いられないかと考えたものである。
表2に海老川流域の単独処理浄化槽を用いている家庭を対象に作成した生活排水の環境家計簿の例を示す。表1の該当欄を見ると、公共用水域に流入する1人あたり汚濁負荷量は、5.2
g-COD 人-1 日-1(=5,200 mg-COD 人-1 日-1), 3.9 g-TN 人-1 日-1(=3,900 mg-COD 人-1 日-1), 0.43 g-TP 人-1 日-1(=430 mg-TP 人-1 日-1)と算定されたことが分かる。これを、し尿、風呂、台所、洗濯等に配分し、さらに家庭における各種の汚濁負荷排出削減対策による公共用水域に流入する1人あたり汚濁負荷量の削減量を算定したのが表2である。
(出典の表では、ここでは、負荷割合を単純に環境省(2002)のBODの割合で配分していたが、し尿とその他の負荷を区分して、負荷割合を算定し直してある。)
表2 生活排水の環境家計簿(海老川流域、単独処理浄化槽)(出典:都筑(2005a)を一部修正)
(表をクリックすると大きな表が表示されます) |
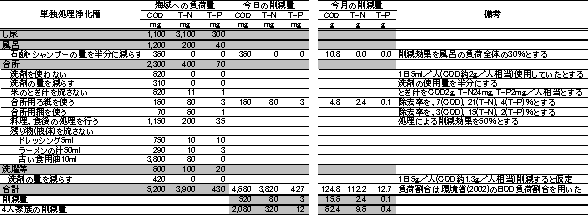
|
(4) 各種の環境家計簿の活用による低負荷排出のライフスタイル
生活排水に限らず、既存の二酸化炭素(CO2)排出量についての環境家計簿をはじめとして、交通、廃棄物などについての環境家計簿を用いることにより、一般市民の生活が環境に及ぼしている影響を定量的に把握することができるようになり、市民と環境との関わり合いが分かり易く見えてくるのではないかと考えている。
それには、行政、専門家による、この種の情報提供が必要となるであろう。地域や家庭により、生活排水処理種類を含め、ライフスタイルは様々であり、行政や専門家は基本的な情報や、ライフスタイルのプロトタイプを提供し、各家庭や各人がその情報を活用して、いわゆる環境にやさしい生活を目指すことができれば、少しでも持続可能な社会に近づくのではないだろうか。インターネットを通じての、この情報提供が、その役割りの一部を担えればと思う。
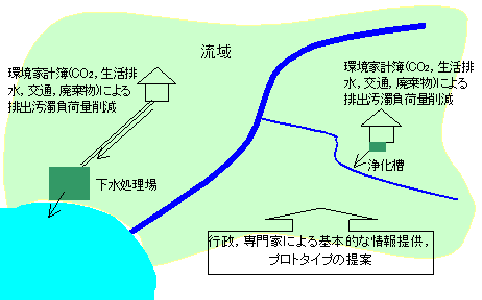 |
| 図2 環境家計簿(CO2,生活排水,交通,廃棄物)を活用した排出汚濁負荷量の削減 |
参考文献
都筑良明 (2005a) 生活排水の環境家計簿、用水と廃水、Vol.47,
No.7, pp.539-545, 平成17(2005)年7月(解説)
(c) 2007, Yoshiaki Tsuzuki
2007.1.12 公開および一部修正